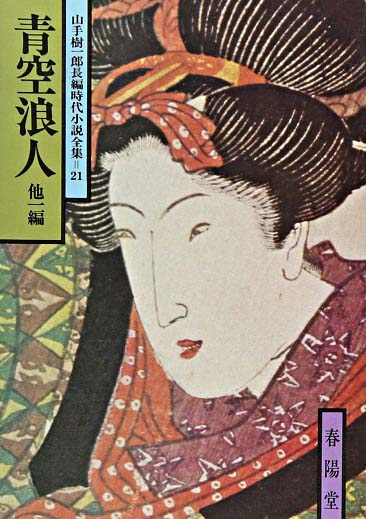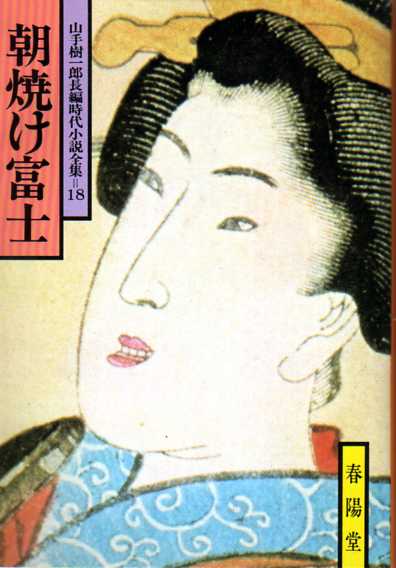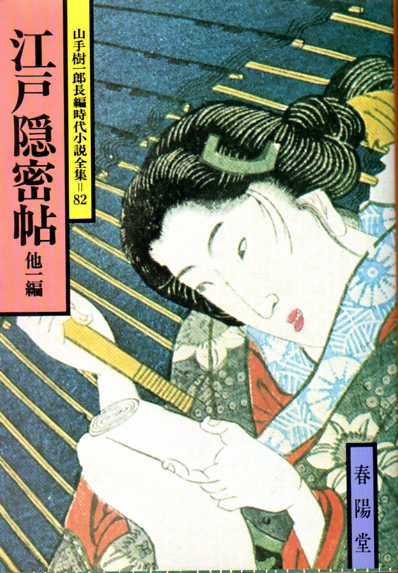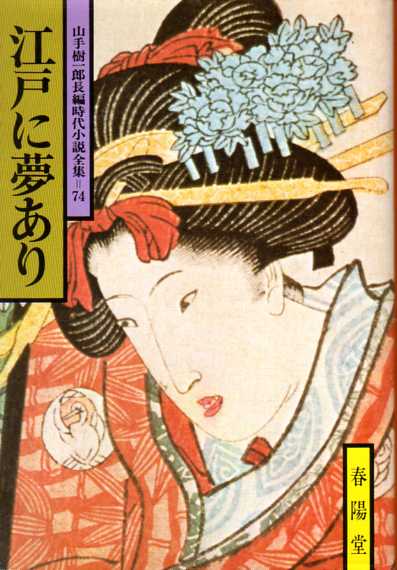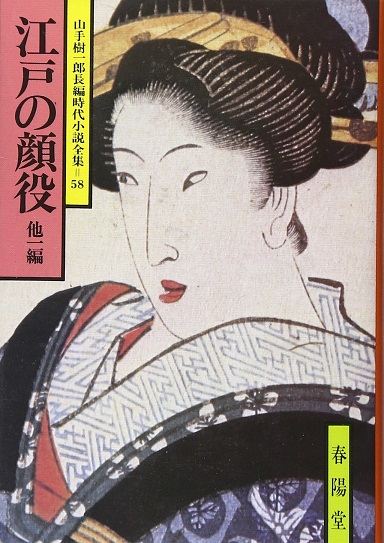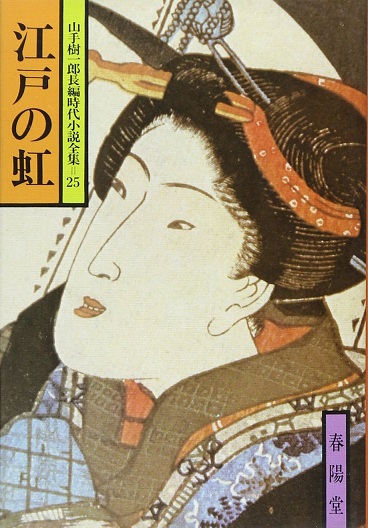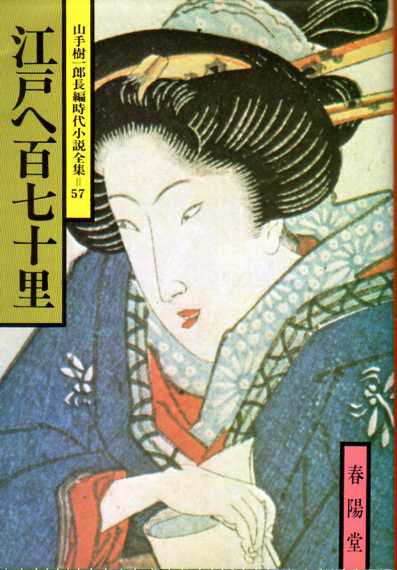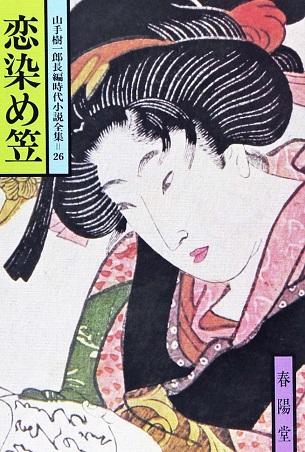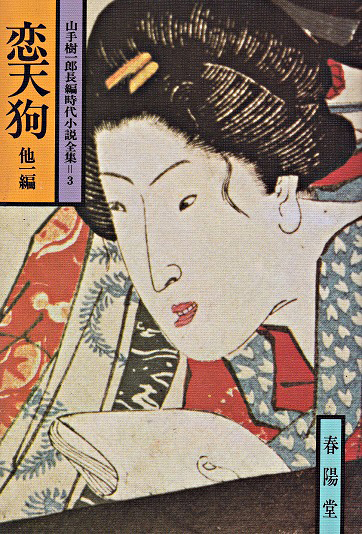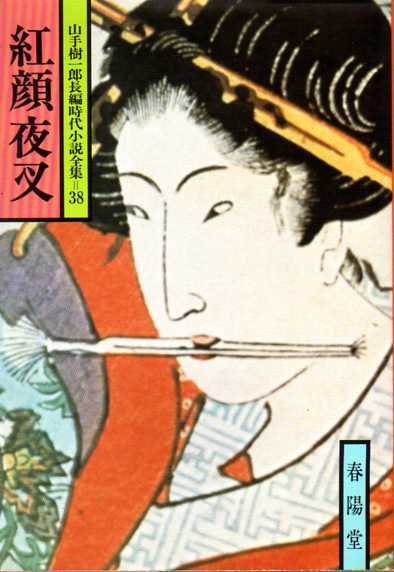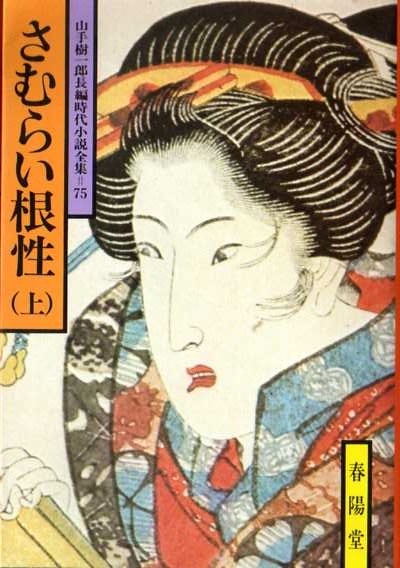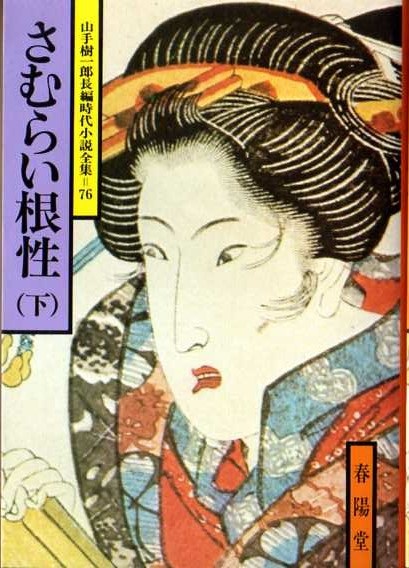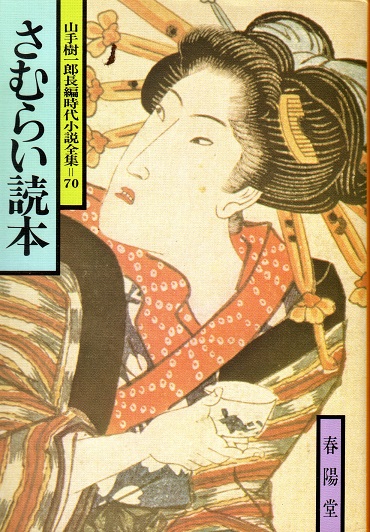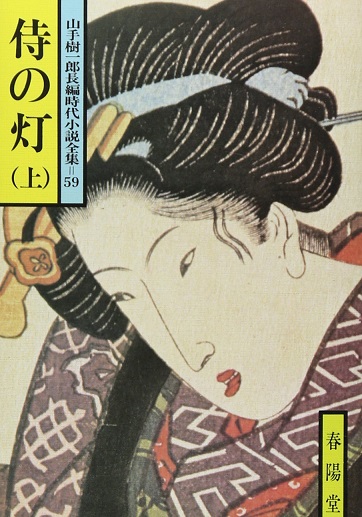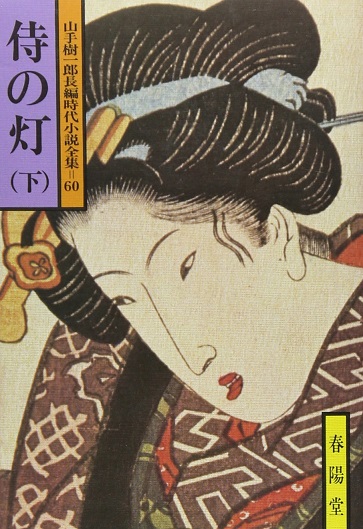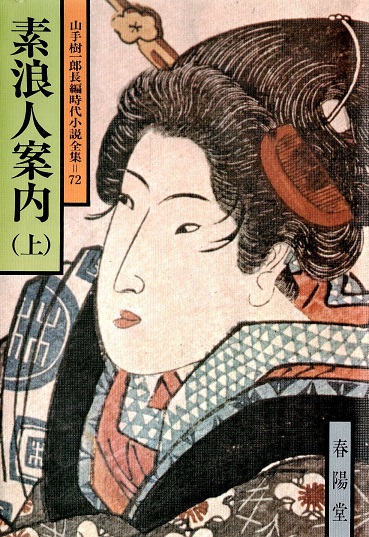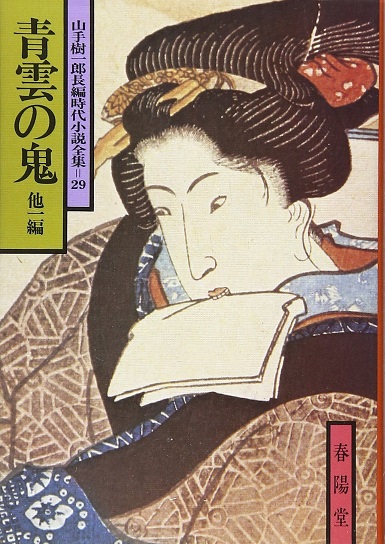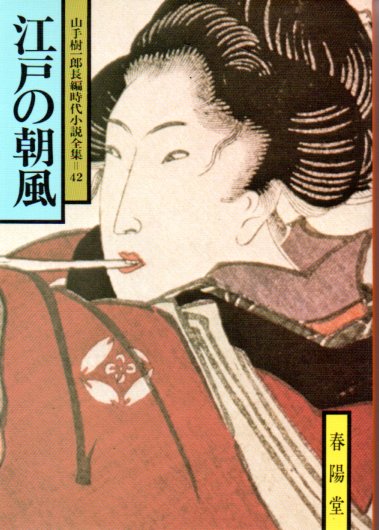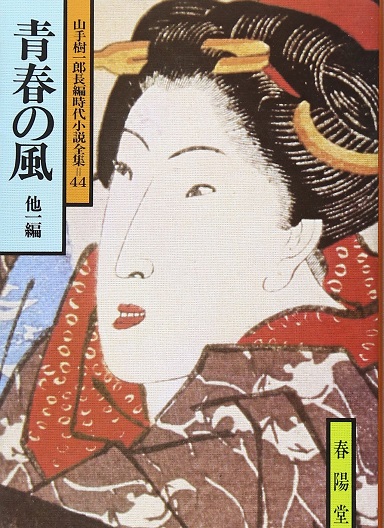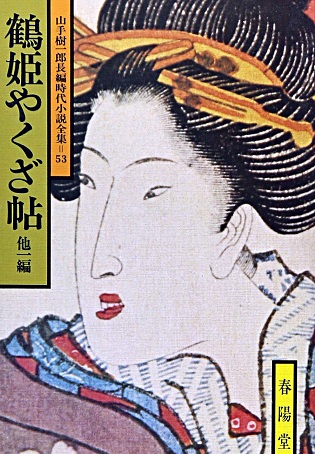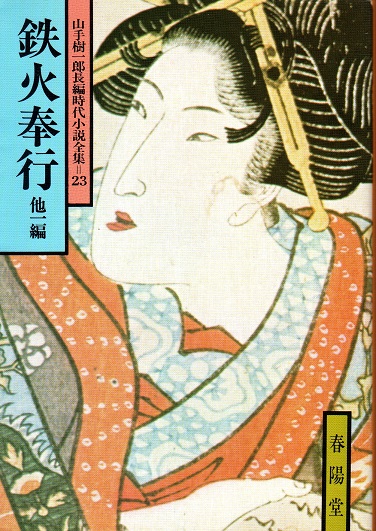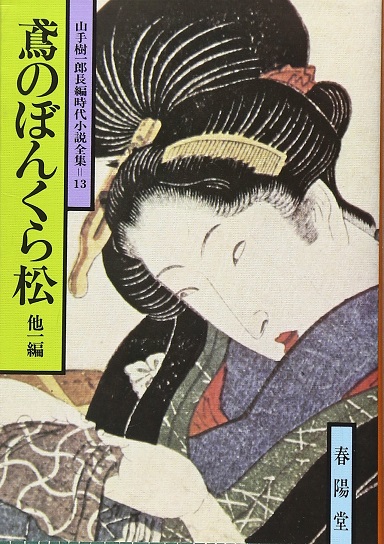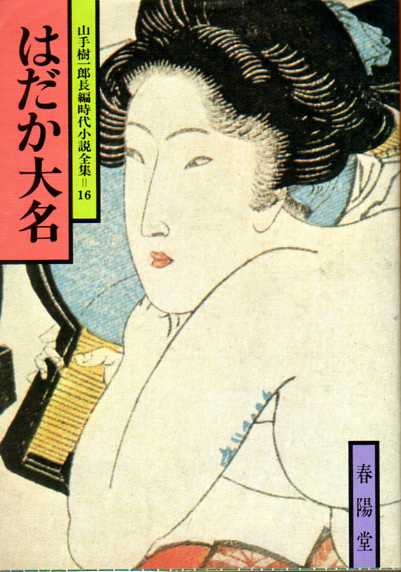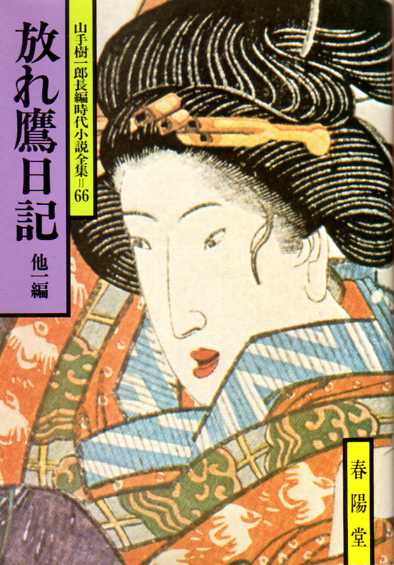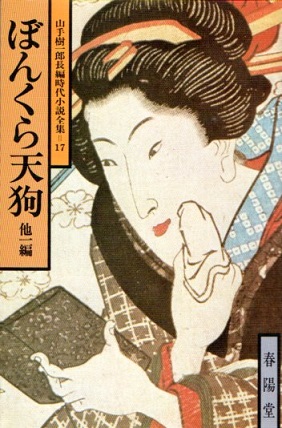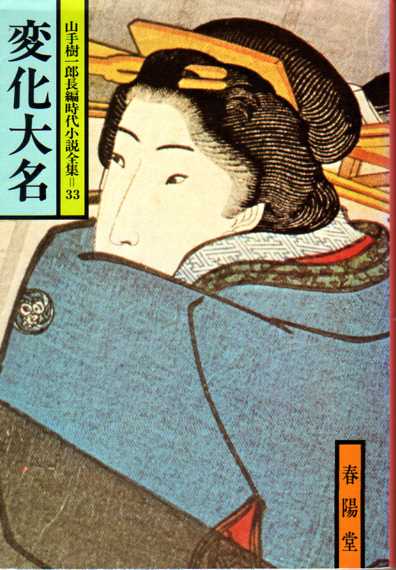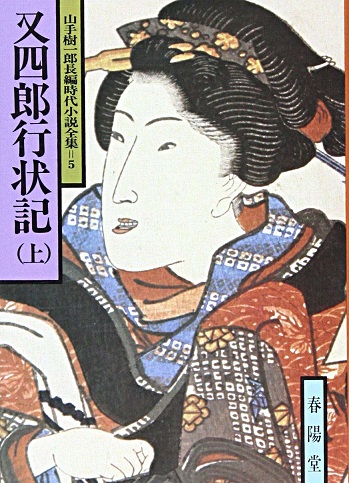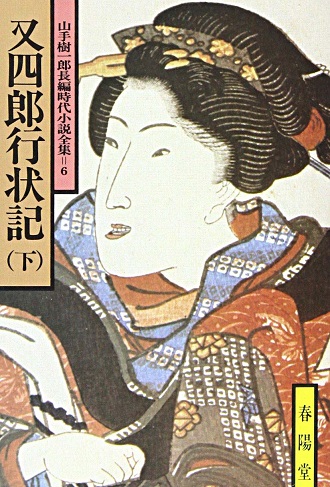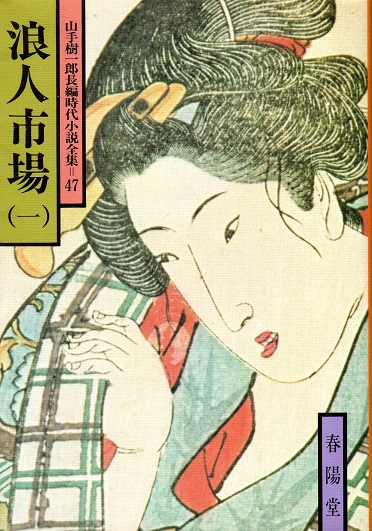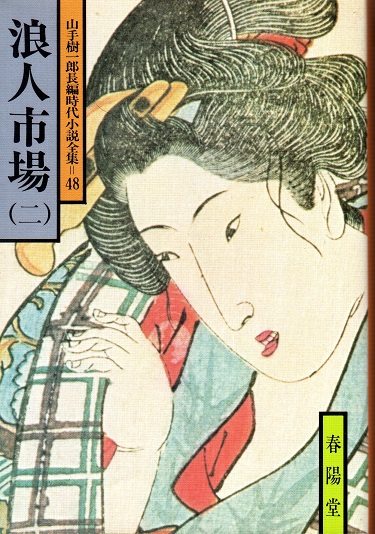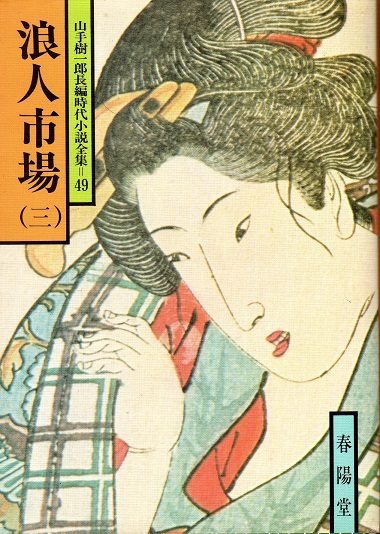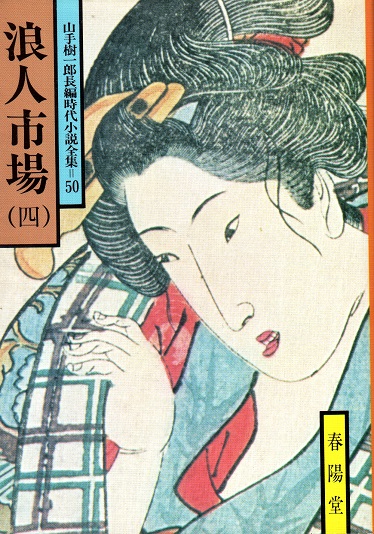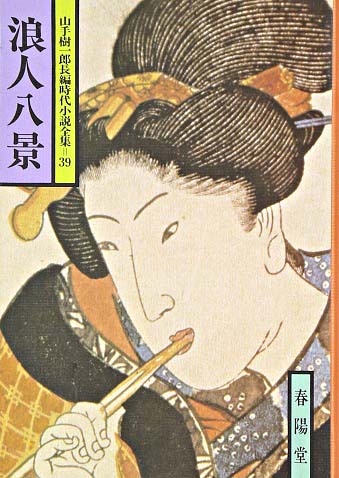1 �����Y��
2 �����X��
3���V��@�����
4 ���R�ƒ��p �����
5.6 ���l�Y�s��L(�㉺)
7 ����痼�݂₰
8 �]�˖������炷�� 1
9 �]�˖������炷�� 2
10 �]�˖������炷�� 3
11 �]�˖������炷�� 4
12 �V�Ҕ����`
13 �̂ڂ珼 �����
14 ���R�̋�����
15 �Ԋ}�Q���Y �����
16 �͂����喼
17 �ڂ�V�� �����
18 �����x�m
19 �Q�l���� �����
20 �f�Q�l���a
21 ��Q�l �����
22 �살�炵�P
23 �S��s �����
24 �J���r�ؖ��E�q��
25 �]�˂̓�
|
26 �����ߊ}
27 �@
28 �t�H���ꎂ�q �����
29 �_�̋S �����
30 �N�����q �����
31 �]�ˌQ���L
32 �J�����ˉ��� �����
33 �ω��喼
34 �]�˂�������l�Y
35 �喼���q
36 ���l�̍�
37 ��a��
38 �g��鍳
39 �Q�l���i
40 �������
41 �����q
42 �]�˂̒���
43 �]�˂̖\���V �����
44 �t�̕�
45 �Q�l��a
46 �V�ۍg����
47�`50 �Q�l�s�� 1�`4
51.52 ��������Y(�㉺)
53 �ߕP�₭���� �����
|
54 �V�ۂ������� �����
55 �V�̉Β�
56 �B���O���u �����
57 �]�˂֕S���\��
58 �]�˂̊�� �����
59.60 ���̓�(�㉺)
61 �������͊� �����
62.63 ���̂܂ꌹ��(�㉺)
64.65 ��Β�(�㉺)
66 �������L �����
67 �����˂Ƌ���
68.69 �_�R����(�㉺)
70 ���ނ炢�ǖ{
71 �O�S�Z�\�ܓ�
72.73 �f�Q�l�ē�(�㉺)
74 �]�˂ɖ�����
75.76 ���ނ炢����(�㉺)
77 ���ނ炢�R��
78 �a���ܘQ�l
79.80 ���ɗ���(�㉺)
81 �j�̐��� �����
82 �]�ˉB���� �����
�ʊ�1 �т̊��� �����
�ʊ�2 ���N�̓� �����
|