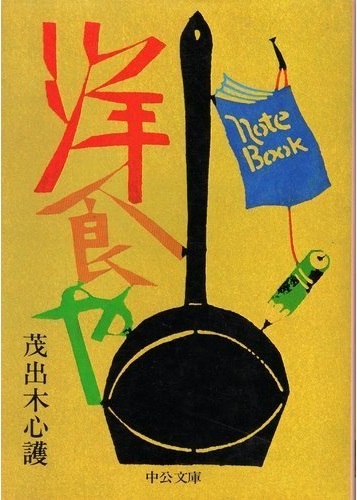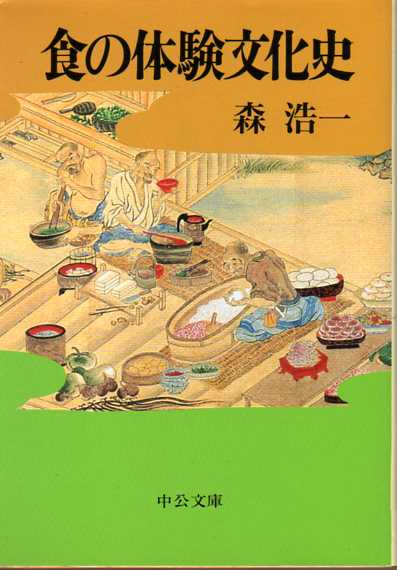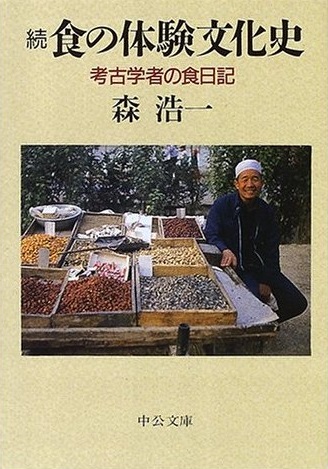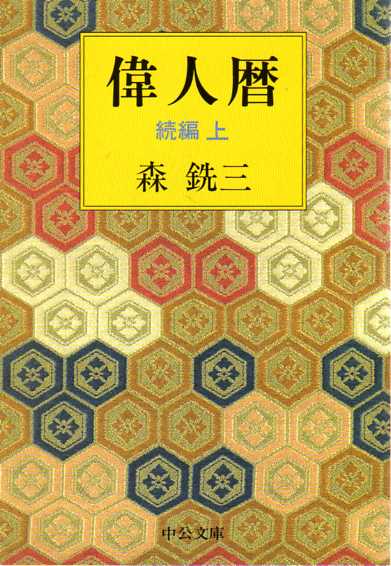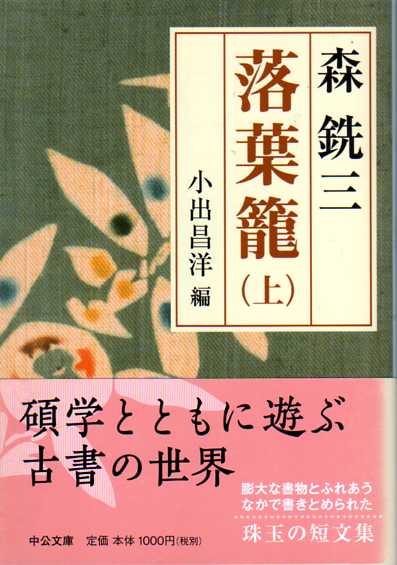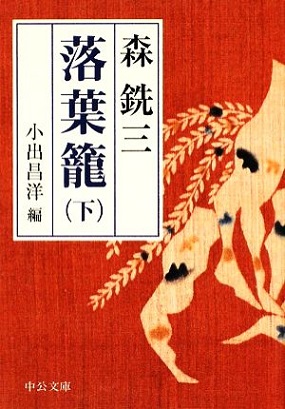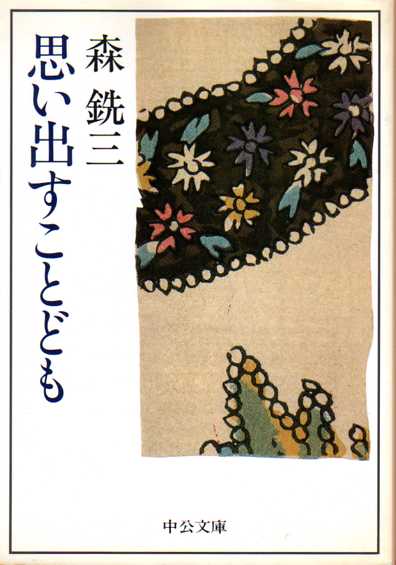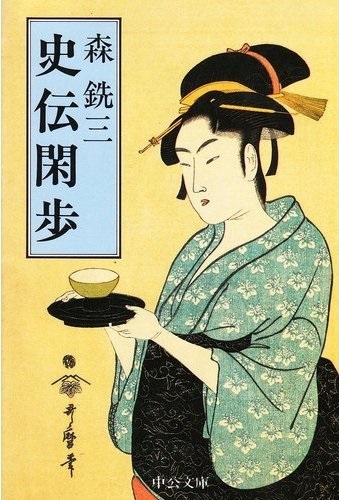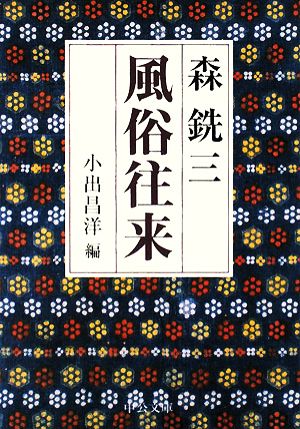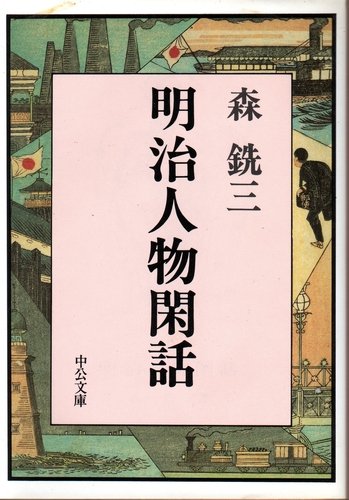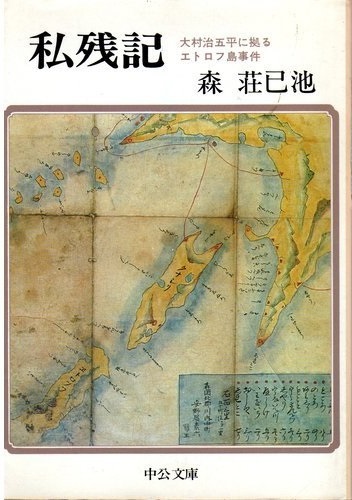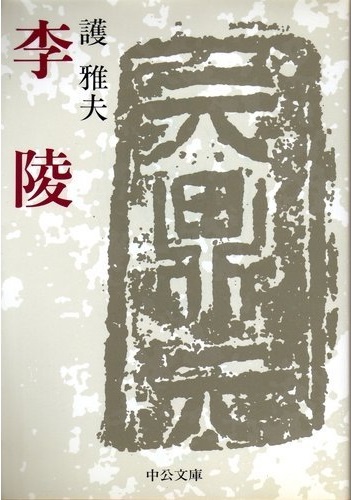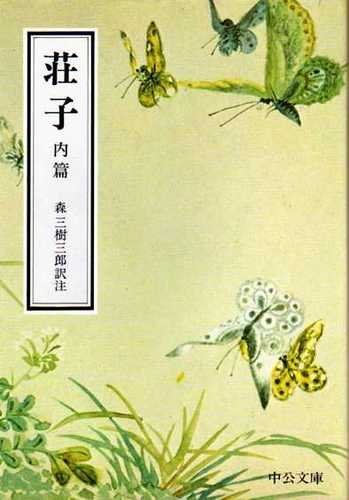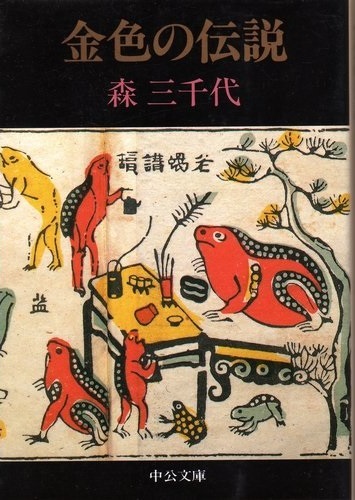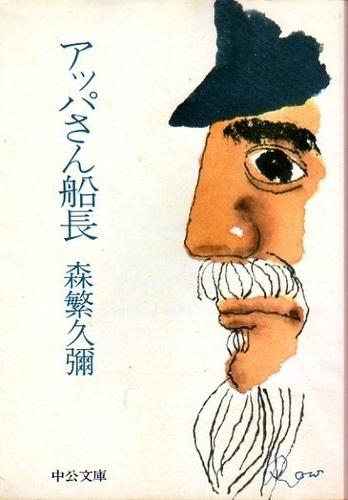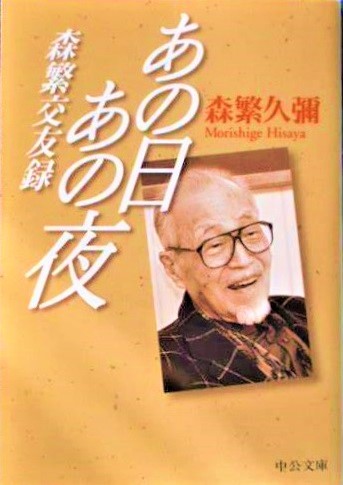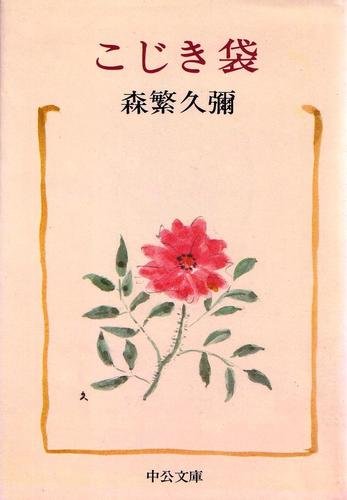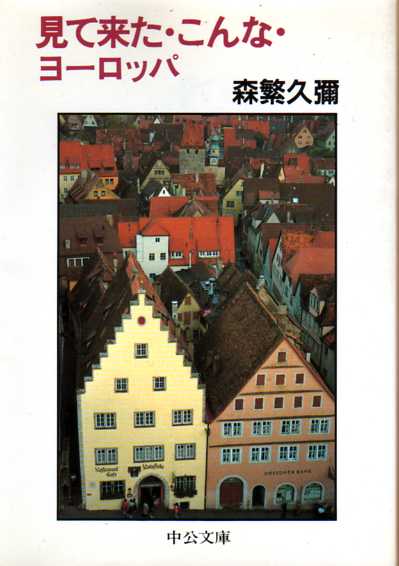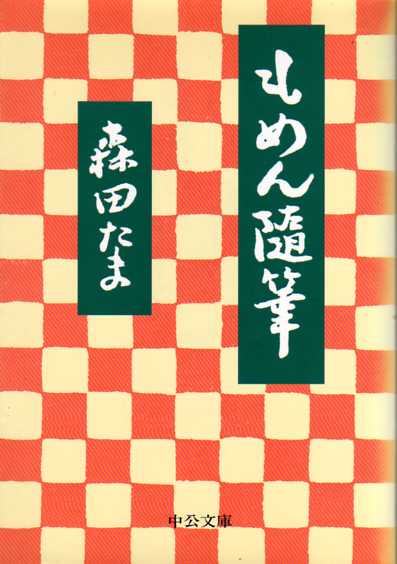絶版文庫書誌集成
中公文庫 【も】
茂出木 心護 (もでぎしんご)
「洋食や」 (ようしょくや)
(画像はクリックで拡大します)
*229頁
*発行 昭和55年
*カバー画・鳥居敬一
*カバー文
日本における洋食やの草分け泰明軒でコック修業ののち、独立して東京・日本橋に“たいめいけん”を持った著者が、失われゆく下町の「洋食の味」を懸命に残そうと努力した、江戸っ子の心意気で綴るエッセイ集。
*解説頁・高田敏子
森 浩一 (もりこういち)
「食の体験文化史」 (しょくのたいけんぶんかし)
森 浩一 (もりこういち)
「続 食の体験文化史 ― 考古学者の食日記」 (ぞくしょくのたいけんぶんかし)
森 銑三 (もりせんぞう)
「偉人暦 続編(上下)」 (いじんれき)
森 銑三著・小出 昌洋編 (もりせんぞう・こいでまさひろ)
「落葉籠 (上下)」 (おちばかご)
森 銑三 (もりせんぞう)
「思い出すことども」 (おもいだすことども)
森 銑三 (もりせんぞう)
「史伝閑歩」 (しでんかんぽ)
森 銑三著 小出 昌洋編 (もりせんぞう・こいでまさひろ)
「風俗往来」 (ふうぞくおうらい)
(画像はクリックで拡大します)
*287頁
*発行 2008年
*カバー・芹沢銈介「梅鉢文卓布」 / カバーデザイン・中央公論新社デザイン室
*カバー文
夏芝居、ロシヤパン、軍楽隊……移りゆく時代の中で著者の心を捉えた芝居、食べ物、新聞・雑誌等の、その時代を彩った「風俗」について綴った随想集。もはや取り返すことがかなわない、懐かしい「日本」が、達意の文章とともに甦る。
森 銑三 (もりせんぞう)
「明治人物閑話」 (めいじじんぶつかんわ)
森 荘巳池 (もりそういち)
「私残記 ― 大村治五平によるエトロフ事件」 (しざんき)
護 雅夫 (もりまさお)
「李陵」 (りりょう)
森 三樹三郎 (もりみきさぶろう)
「荘子 内篇」 (そうじ ないへん)
(画像はクリックで拡大します)
*213頁
*発行 1974年
*カバー画・扇画『胡蝶図』
*カバー文
「内篇」七篇は、荘子その人の思想を確実にあらわしているとされる。その中心となる「万物斉同の説」(絶対無差別論)は、一切の価値を越えて、何ものにもとらわれない自由思想の極限を示している。
*解説頁・森 三樹三郎
森 三千代 (もりみちよ)
「金色の伝説」 (こんじきのでんせつ)
森繁 久彌 (もりしげひさや)
「アッパさん船長」 (あっぱさんせんちょう)
森繁 久彌 (もりしげひさや)
「あの日あの夜 森繁交友録」 (あのひあのよる)
森繁 久彌 (もりしげひさや)
「こじき袋」 (こじきぶくろ)
(画像はクリックで拡大します)
*224頁
*発行 1980年
*カバー文
”こじき袋”とは、見聞の一切をつめこんでおく役者の頭の中の袋のこと ― 馬の脚からアナウンサーとなって、決意も新たに渡った満州、そして録音機を肩に遠く遥かな旅をつづけた蒙古など、戦前の異郷での日々をはぎれのいい語り口でつぶさに綴る森繁自伝序章。
*序・大宅壮一
森繁 久彌 (もりしげひさや)
「見て来た・こんな・ヨーロッパ」 (みてきたこんなよーろっぱ)
森田 たま (もちたたま)
「もめん随筆」 (もめんずいひつ)
(画像はクリックで拡大します)
*304頁 / 発行 2008年
*カバーデザイン・中央公論新社デザイン室
*カバー文
男と女のこと、大好きな着物のこと、家族のこと、そして内田百閒や宇野千代たち交流のあった文士のこと……自由な雰囲気の札幌に育ち、文学を志して上京、結婚して大阪に住まう。女性エッセイストのさきがけともいうべき森田たまが現代的かつ自由な視点で描いた第一エッセイ集。
*解説頁・市川慎子
*新潮文庫版(サイト内リンク)